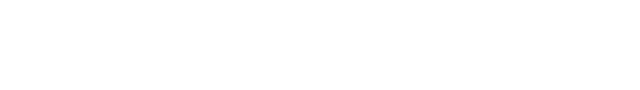80. 違和感だらけの映画「閉鎖病棟」
先日、映画「閉鎖病棟―それぞれの朝―」を鑑賞いたしました。
この作品は、作家で精神科医の帚木蓬生先生の小説「閉鎖病棟」を映画化したものです。私は原作本を約10年前に拝読し、精神科病棟で繰り広げられる人間模様を描いた作品でとても感動的な内容だったのを覚えています。また、帚木先生は森田療法にも造詣が深く、昨年7月の「森田正馬没後80年記念講演会」にて特別講演をされました(9話参照)。それだけに、この映画作品の上映がとても待ち遠い気持ちでした。
しかしながら、実際この映画を拝見し、残念ながら期待外れと言わざるを得ませんでした。
確かに、笑福亭鶴瓶さんや綾野剛さん、そして小松菜奈さんの演技は見事でした。特に鶴瓶さんはこの作品の役作りのために7キロも減量されたらしく、NHKの番組「家族に乾杯」とは全く違う鶴瓶さんに、とても感銘を受けました。
私が残念と思ったのは、この映画の舞台となる病院の体質や精神科医療の考え方ががいかにも時代錯誤としか思えないことです。原作が出版されたのは1995年。まだ精神科病院はまだ隔離収容という考え方が色濃く残っていた時代です。一方で、この映画の時代背景は、現代と推測されます。登場人物の一人がデジタル一眼レフカメラを所持しており、しかも病院のエレベータに「当事者研究」のポスターが貼ってありましたから(「当事者研究」が全国的に広がりを見せたのは、ここ10年のことです)。現代では、数々の新しい抗精神病薬が登場し、精神科医療での代表的な疾患である統合失調症は、適切な治療により社会復帰が十分可能という考え方が定着してきました。長く入院を続けてきた患者さんが地域へ退院されることも珍しくなくなりました。しかしながら、この映画作品では、原作当時の精神科医療の考え方がそのまま使われてしまったことに大きな違和感を覚えます。
それだけでなくこの映画では、個々の患者があまりにも特徴的で、誇張されたように演じられているため、精神科病棟=「怖い」というイメージを抱かせてしまいます。これでは、精神科医療への偏見がさらに助長されるのではと懸念します。この映画では病棟でしばしば器物破損や暴力事件が生じるかのような描写がされています。実際の精神科病棟では、滅多にこのような事件は起こりません(私が約15年単科精神科病院に勤務してきた体験から述べたものです)。
しかも、舞台の精神科病棟の管理体制があまりにも「ずさん」です。例えば、とある患者が突然失踪したシーンです。通常の精神科病院なら、万一閉鎖病棟で患者さんがいなくなった場合、多くの職員が患者さんを探し出しますし、万一見つからない場合は警察に届出をします。しかしながらこの映画では、その患者を捜索するシーンは一切出てきません。この病院は、失踪した患者をそのまま放置したのではと感じてしまいます。その他にも、首をかしげたくなるシーンが数々登場しますが、ネタバレになるため割愛します。いずれにせよ、これを鑑賞したお客さんが精神科医療に対し不信感を抱いてしまうのでは、と危惧しています。
この映画を制作した方々は、最近の精神科医療の事情についてきちんと学ばれたのでしょうか?非常に疑問に思います。もはや現代の精神科病院は、「居場所をなくした人々が、ここで出会い」という場所ではありませんから。
【引用文献】
映画「閉鎖病棟―それぞれの朝―」パンフレット