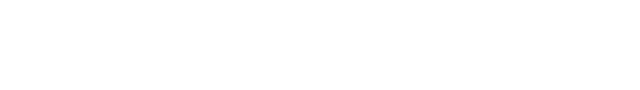323. 「自分らしく パニック障害と共に生きる」後篇
(前篇322話の続きです)
元プロ野球選手・小谷野栄一さんのエッセイ本「自分らしく パニック障害と共に生きる」1)には、パニック発作や不眠で悩んでいた小谷野さんに対して、「何回吐いたっていい。とにかくバッターボックスに立ってみよう」と指導した福良淳一さんの証言も載せられています。
私の指導者経験のなかでもパニック障害の選手というのは(小谷野)栄一が初めてだったので、どうしたら良いものか正直わかりませんでした。(中略)突出した実力を持っていた選手でしたので、なんとしても這い上がってほしい、そんな思いから試合で起用するにしても、試行錯誤を重ねたように記憶しています。(中略)フェニックス・リーグで栄一を起用したのは、人数が足りなかったからということもありますが、“逆療法”みたいな考えもありました。とにかく打席に立たせる。何かあって試合の進行が遅れた時には、私が謝れば済むんだと。
福良さんは「逆療法」という言葉を用いていますが、私はこのストーリーを拝読し、「森田療法」と類似するのではと感じました。
森田療法について一言で説明するのは難しいですけれども、当院ブログ139話に掲載した、高良武久先生の「あるがまま」についての説明2)が、森田療法の真髄ともいえるため、引用します。
「あるがまま」の第一の要点は、症状あるいはそれに伴う苦悩、不安を素直に認め、それに抵抗したり、否定したり、あるいはごまかしたり、回避したりしないで、そのまま受け入れることである。
第二の要点は、症状をそのまま受け入れながら、しかも患者が本来持っている生の欲望にのって建設的に行動することで、これがたんなるあきらめと異なるところである。
また、森田療法では、「症状不問」という技法を取ることがあります(197話)。これは、患者さんが訴える症状については聞くけれども、それを治すべき対象として大きく取り上げることはしない、という構えです。福良さんは、小谷野さんの嘔吐や過呼吸などの症状については不問とし、とにかくバッターボックスに立てばそれでよいと指導し、実際に小谷野さんが打席に立てたことを評価し、励まし続けました。
パニック障害では、「発作が起こってしまったら」という予期不安から、外出などを避け、症状に視野狭窄することでますます予期不安が高まるという悪循環(森田療法でいう「精神交互作用」)に陥ることがよくあります。このため、森田療法では、このような悪循環を打破するために、不安がありながらも建設的な行動をしていくよう指導していきます(注)。小谷野さんの場合、パニック発作やそれによる予期不安が強い中、福良さんの言葉を受け、「やっぱり野球を続けたい」「死に物狂いで結果を出そう」という欲求(「生の欲望」)にのって、症状がありながらもプレーをしていくという行動を続けた結果、ご自身の本来の実力が遺憾なく発揮され、意外にも好成績を残せたという結果になったのではと考察しています。
小谷野さんは、その後もパニック発作を抱えたままプレーを続け、打点王1回(2010年)、ゴールデングラブ賞3回(三塁手部門:2009年、2010年、2012年)、ベストナイン1回(三塁手部門:2010年)を受賞するなど活躍を見せることになります。これにつきましては驚嘆に値します。
今回ご紹介した、小谷野さんのエッセイ本「自分らしく パニック障害と共に生きる」は、そのほかに、小谷野さんを支え続けた大学の恩師や一人の少年が登場するなど、感動的な内容になっています。ご興味のある方は是非お読みください。
【引用文献】
1) 小谷野栄一:自分らしく パニック障害と共に生きる.潮出版社,東京,2019.
2) 高良武久:森田療法のすすめ[新版].白揚社,東京,2000.
(注)とはいえ、本人の不安や抑うつ等を配慮せずに、「建設的な行動」ばかりを指導するのはあまりよくないというのが私の最近の考え方です。治療の場で「行動」の有無を重視してしまうと、行動できない本人を責める姿勢になりかねず、本人の治療のモチベーションを下げ、しまいにはドロップアウトに至る恐れもあります。特に、抑うつ症状があるケースに「建設的な行動」を促すのは推奨されません。まずは、本人の不安、抑うつに対し薬物療法を行うなど、ゆっくりとやっていくほうがいいように思えます。ちなみに、当院ブログの初期によく登場していた「恐怖突入」という言葉も、最近では使わなくなりました(森田療法の創始者・森田正馬先生も晩年ではその言葉を使われなくなったという話を聞いたことがあります)。
一方で小谷野さんのケースでは、このフェニックス・リーグに出場しない場合、チーム自体が試合に出られなくなるうえ、小谷野さん自身もこのシーズンでは欠場が多いため、戦力外通告を受ける恐れが十分にありました。パニック発作やそれに対する予期不安、不眠等が強い中、いわゆる「背水の陣」で出場という建設的な行動を選ばざるを得なかったところもあったものと思います。そんな中、福良さんのあたたかい助言やご本人の「野球を続けたい」という強い欲求が功を奏し、思わぬ結果を残せたのではないかと私は勝手に考えています。