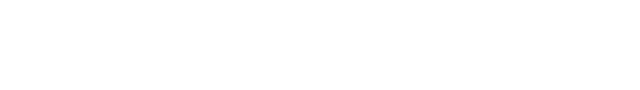324. やはり紙の地図がいい
自宅には、県別の道路地図や広域の地図、大都市の地図など、紙の地図のコレクションを並べています。
私の地図好きは小学生の頃からで、地図を読むのが好きだった、祖父(故人)や父の影響が強いものと思っています。
長距離のドライブをするときは、必ず紙の地図を使って、ルートなどを予習します。そしてドライブ当日には必ずこれらの地図を持参します。私の車にはナビはあるものの、ドライブの際にそれを使用することは少ないです。私の進みたいルートを指定してくれないことが多く、かえってストレスになるためです。ただし、おおよその所要時間を把握する目的や、複雑な高速道路のジャンクションを通過する場合、道路の複雑な市街地を走行する場合は、ナビを併用することもあります。
また、大都市に旅行や出張へ行く際には、その都市の冊子の地図をカバンの中に入れています。宿泊するホテルにて、持参した地図を眺め、プランを立てるのも楽しいものです。
最近では、パソコンやスマホでも地図が無料で自由に見られるようになっていることから、わざわざお金を払って紙の地図を買わなくていいのではないかと思われるかもしれません。しかし、長年紙の地図を使い続けた私にとって、ネットの地図がどうしても使いにくいのです。ドライブのルートを調べる際に、紙の地図であれば、ページをめくれば済みます。一方で、ネットの地図では、道路を確認する際に縮小や拡大を繰り返さなければならず、その操作がどうしても煩わしく思ってしまいます。ただ、紙の地図では、細かいお店などの情報が載っていないとか、古い地図では最近開通した道路が載っていないという欠点があります。これらの情報を調べる際に、ネットの地図を補完的に使うこともあります。私がよく使うのは、ゼンリンの地図アプリです。これは、地図の最大手メーカーであるゼンリンが作成したものであり、ネットの地図の中では比較的見やすいと思っています。一方で、ネットの地図の中では最もポピュラーとも言える某G社のマップは、私は一切使いません。某G社のマップ自体が非常に見にくい(注)だけでなく、匿名で罵詈雑言書き放題のお店等のレビュー(クチコミ)は読んでいて非常に気分を害するからです。
ところで最近、山梨県の地図(県別マップル)を購入しました。山梨県のご当地Vチューバ―さんの動画をみて、この地域に興味を持ったためです。今は、この地図のページをめくって、紙上旅行を楽しんでいます。そのうち、山梨県へドライブに行けるといいなと思っています。
(注)当院ホームページの「アクセス」ページには、当院開業当初は某G社の地図を載せていました。しかし、初めて来院される患者さんが道に迷われるということが頻回にありました。某G社の地図が分かりにくいためではないかというご意見もあったことから、リーフレットなどに載せた地図を「アクセス」ページに付け加え、更には某G社の地図からヤフーの地図に切り替えました。なお、トップページに表示している某G社の地図もヤフー地図に変更したかったのですが、残念ながら変更できない仕様になっているようであり、現在もそのままになっています。
【おまけ(私の地図コレクション)】
県別マップル 私が興味を持った県のものを所有している。このため、私の好きな福井県や、森田正馬先生の生誕の地である高知県も持っている。縮尺が1:30000(一部1:60000)で大きく、見やすいため、ドライブではこれを主に使用している。中には7年前に購入したものもあり、アップデートのため買い換えたいけど、1冊3000円弱とやや高いため、躊躇しているところである。
大都市の地図とツーリングマップル(右にあるリングの冊子) 大都市の地図は、その都市へ旅行に行く際に携行する。ツーリングマップルについては後述。
今年の元日に、伊豆方面へドライブ(301話)に行った際に使用した地図。左がツーリングマップルR。もともとライダー向けの内容であるが、ドライブの際にも十分活用できる(有料道路の料金の表示がバイク向けになっているので乗用車使用の場合は要注意)。リングでとじられており、開いたままにできるのでドライブでは非常に愛用している。道路や立ち寄り地などの情報が非常に詳しい。ただし、縮尺が1:120000と小さく、道路の細かい様子が見にくいため、静岡県の県別マップルを併用した。
4月下旬に会津経由で山形へドライブ(318話)した際に使用した地図。東北のライトマップルで大雑把に道路を把握し、細かい情報については福島県、山形県の県別マップルを使用した。
最近買った、山梨県の県別マップル。恥ずかしい話だが、「元気甲斐」「高原野菜とカツの弁当」などの駅弁で有名な小淵沢は、現在北杜市の一部であることを、この地図を見て初めて知った。このような情報は、紙の地図でないとなかなか得られないものである。