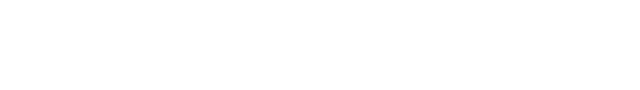377. 深刻な読書離れ、書店減少
毎月自宅に届く雑誌「致知」の6月号1)の特集は「読書立国」というタイトルでした。この雑誌では、様々な分野で活躍されている方々による記事が掲載されています。その中で特に印象に残った部分を抜粋します。
・江戸時代や幕末維新期の日本人ほど、読書をする民族は世界になかった。江戸時代の識字率は60-70%で、同じ時代の西洋列強に比べてはるかに高かった。江戸末期に江戸に来たイギリス人たちは、普通の庶民が本を立ち読みしている姿を見て、「この国は植民地にできない」と思ったという。
・しかしながら、最近では日本人の読書離れが著しい。スマホの普及やデジタルコンテンツの充実の影響である。それにより読解力や語彙力が低下している。
・更には、書店の減少も深刻な問題だ。1999年、日本の書店は約22000店あった。それが2014年に14000店になり、令和7年現在では1万店を切り、減少はさらに加速している。
また、東北大学加齢医学研究所教授の川島隆太先生の記事には、脳科学が明らかにしたデジタル端末の弊害について述べられています。スマホなどでインターネットを利用する時間が長い子供ほど、脳の発達が阻害されるという研究結果があり、具体的には、言葉を司る前頭葉と側頭葉の発達が右脳も左脳も止まり、白質も大脳全体にわたって発達が止まっていたとのことです。また、デジタル端末を用いて勉強する時間が長い子供ほど成績が下がっているという研究結果もあったそうです。すなわち、勉強していない子供に比べ、デジタル端末で長い時間勉強した子供のほうが成績は悪くなったということです。そのお話には大変驚きました。
致知6月号を読んでいる時期に、ちょうど下野新聞で「子どもの『不読率』悪化」という記事2)を見つけました。2024年度の栃木県内の不読率(1か月に1冊も本を読まない子の割合)は、小学生8.8%、中学生21.5%、高校生53.5%で、いずれも前年度より悪化したとのことでした。県内の半数以上の高校生が1か月に1冊も本を読まないということには驚愕しました。
確かに、私が電車に乗っていると、周囲の乗客の殆どがスマホを見ています。昔は車内では本や新聞を読む人が多かったのですが、今や少数派になりました。また、栃木県都の宇都宮市には、かつては大きい書店がたくさんありました。しかしながら徐々に数が減っていき、「北関東最大規模」と呼ばれていた喜久屋書店も昨年9月に閉店になってしまいました。この書店は、専門書コーナーがそれなりに充実していただけに大変残念です。
先述の致知や下野新聞の記事で「読書は精神力を強くする」「読書は言葉や感性などを育てる」と述べられていました。読書をせずにスマホばかりに興じてきた子供たちがこのまま将来我が国を担うことになると、果たしてこの国は大丈夫だろうか?と思わず憂慮してしまいます。
と、偉そうなことをいう私も、ついスマホでX(旧ツイッター)やYouTubeなどを見て過ごしてしまっていることについて反省し、最近では朝の出勤前に読書の時間を設けるようにしました。また、語句を調べる際はネット検索に頼らず、紙の辞書(広辞苑、ジーニアス英和辞典)を用いるよう努めているところです。
1) 致知出版社ホームページ
https://www.chichi.co.jp/info/chichi/backnumber/2025/202506/
2) 下野新聞 2025年6月14日3頁 子どもの「不読率」悪化