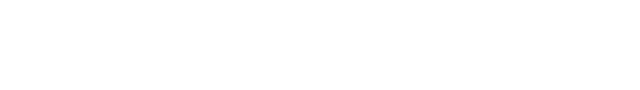389. 製薬会社のMRさん向けの講演
先週、とある製薬会社の医薬情報担当者(MR)さん向け社内研修会にて講師をさせていただきました。当日、会場(大田原市のとある会議室)にはお二人のMRさんがいらっしゃいました。他のMRさんはリモートで参加されました。
当日は「睡眠薬と不眠症治療について」話してほしいとのことであり、タイトルは「睡眠薬の適正使用と不眠障害の治療戦略」といたしました。
今回の講演では、「睡眠薬の歴史」「睡眠薬をめぐる諸問題」「不眠障害の治療戦略」についてお話ししました。その中で最も強調したかったのは、ベンゾジアゼピン受容体作動薬のリスクです。
近年では、ベンゾジアゼピン系と非ベンゾジアゼピン系を合わせて「ベンゾジアゼピン受容体作動薬」と呼ぶことが増えています(以下、「ベンゾ」と略します)。ベンゾは確かに不眠や不安に対して速やかに効果を発揮することから、令和の現在でも多くの医師により処方されています。しかし一方で、依存性、転倒(→骨折)、脱抑制、せん妄などの様々なリスクがあります(37、38、39話)。特に依存性の問題は深刻であり、保険で定められた用法用量を守っているのにかかわらず数週間~数か月で「常用量依存」になることがあり、ベンゾを始めるのは簡単なのに、やめるのが難しいという事態になることをよく経験します。
ところで、薬物依存といえば、皆さんは覚せい剤、大麻、麻薬、危険ドラッグなどの違法薬物を思い浮かべるでしょう。しかし最近では、依存症の医療において、市販薬や処方薬といった、合法薬物が約半数を占めるという調査結果1)があります(余談ですが、最近芸能人逮捕でマスコミが過剰に騒いでいる「大麻」はわずか数%に過ぎません)。睡眠薬・抗不安薬の乱用ランキングのベスト3は、エチゾラム(デパス)、ゾルピデム(マイスリー)、フルニトラゼパム(ロヒプノール、サイレース)1)。処方薬依存は、安易にベンゾを処方する医師の責任です。
エチゾラム(112話)は様々な診療科で気軽に処方されてしまうきらいがあります。エチゾラムは依存性が強く、一度始めたエチゾラムがなかなかやめられないというケースによく遭遇しています。筋弛緩作用が強いため転倒するリスクもあり、高齢者では特に危険です。ゾルピデム(229話)は、「非ベンゾジアゼピン系」に属しており、発売当初は「依存や転倒のリスクが少ない」と喧伝されていました。しかしその後の研究で、依存性や転倒のリスクはベンゾジアゼピン系と変わりないということが明らかになっています。かつて、とある医師が「ゾルピデムは依存がない」と豪語したという話を聞いたことがあります。しかしそれは大間違いということです。その他、異常行動を起こすこともあり、海外では死亡例も報告されています。
以上から、睡眠薬を処方する場合は、なるべく「ベンゾ」は避け、安全性の高い不眠症治療薬(オレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬)を選択すべきと考えております(軽度の不眠の場合には漢方を処方する方法もあります)。
とはいえ、不眠症の患者さんを診たらすぐさま睡眠薬を処方するという治療者の姿勢も適切とは言えません。あくまでも睡眠薬は補助手段。睡眠衛生指導や精神療法も大切であることをこちらの講演で述べさせていただきました。睡眠衛生指導の例は下記のスライドの通りで、不眠症に対する森田療法的生活指導についても解説いたしました(120、121話)。
(注)あくまでも上記は、併存疾患(うつ病、双極症、統合失調症など)のない不眠障害に対する指導内容です。併存疾患が明らかな場合には、その治療を優先しなければなりません(例:うつ病の極期のケースでは、休養等の環境調整、抗うつ薬の処方など)。
講演の後は、数名のMRさんからご質問をいただくなど活発なディスカッションになりました。私も大変勉強になりました。
誠にありがとうございました。
1) 松本俊彦,宇佐美貴士,船田大輔ほか:全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査.令和4年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)分担研究報告書:pp77-140.