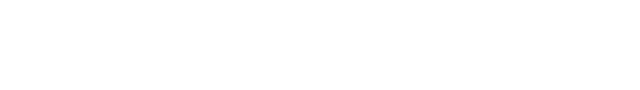12. 上医賣術下医賣薬
(前回の続きです)
森田正馬先生は診療に際して、患者の訴える症状だけでなく人間全体を診るべきだと主張されました。一方、目先の症状だけにとらわれて、それに対し安易に薬を出す治療者の姿勢を厳しく批判してこられました。
森田先生は次のように述べられています(すべて森田正馬全集第七巻(白揚社 1975)より。なお旧漢字は現在の漢字に変えています)。
「病といへば」薬といふ事は、古来よりの習慣に捕はれた誤想である。病の治療といふ事には、多くの場合、薬は単に医療の補助をするのみである。服薬を必要としない又は其有害な場合は甚だ多い。(中略)今日「病といへば薬」という病人と医者との関係から、多くの患者が徒らに無用の薬を呑まされて居るといふ事は、既に心ある人々はよく知つて居るべき筈である。(p.203)
当世の学者は、病人を見れば、必ず一方には、徒らにその病症の原因というものを突きとめようとし、又一方には、強いて其症状を除去しようとして、何れも共に、その病人の人間という事を忘れ、角を撓(たわ)めて牛を殺し、人参を呑んで首をくゝる・というやうな事(注:かえってその病人を不幸な目に合わせること)が多い。(p.400)
古人は、「医者は同時に、哲学者でなければ、不完全たるを免れない」といつた事がある。単なる物質医学で、思想のない学究者は、屢々(しばしば)危険である。(p.404)
残念ながら、森田先生が亡くなられてから80年経った現在でも、「物質医学」、すなわち「薬を売る医学」の傾向は変わっていません。
確かに、現代では、高い有効性を持つ向精神薬が多く発売され、精神科医療は格段と進歩しました。殊に、森田先生の時代では治療の施しようのなかった、統合失調症や双極性感情障害については有効性の高い治療薬が開発されました。これにより病気から回復し、元気に生活されている患者さんも数多くいらっしゃいます。神経症についても、薬物療法を補助的に用いることにより治療が円滑に進展できるようになったのも事実です。
しかしながら、薬物療法には限界があります。例えば、環境の要因により反応性に抑うつが生じる「適応障害」に対しては、薬の効果は極めて限定的です。職場で上司からパワハラを受け、気分が落ち込むのは、一般的には正常な反応です。このような方に薬を処方しても、本人の悩みが解決することも気分が晴れやかになることもあり得ません。薬は、人の苦悩を速やかにきれいさっぱり除去するような魔法の作用はないのです。
しかし、上記のような正常な気分の反応を「病気の症状」とみなし、薬で除去しようとする医療が横行しています。そんな中「薬漬け」も深刻な問題です。眠れない、不安だ、ドキドキする・・・などの症状をとにかく消そうとして、足し算のように薬を増やしてしまう。そうするといつの間にか薬の種類が多くなってしまいます。これが多剤多量薬物療法です。場合によっては、それらの薬の副作用で苦しむ患者さんもいらっしゃいます(その副作用を消す目的で、更に薬を追加する治療者がいるのも事実です)。これはまるで、上記の森田先生のお言葉・2番目の如くです。
症状の話だけしか聞かず、薬を出すことしかしない治療者は、単なる「薬の売人」にすぎません。それよりも、その症状の裏にある生活状況、家庭環境、本人の性格傾向、既往歴などなど詳しく聞き、患者さんの全体像を把握することが大切です。そして、薬物療法だけに偏らず、生活指導や精神療法をうまく織り交ぜ、患者さんが「自分らしい生活」を送れるようになるよう援助していく。これが森田先生のおっしゃる「術」に相当するのではないかと考えております。
当院でもこのような「術を売る」医療を行なっていきたい所存です。
【注】私は薬物療法を完全否定することは一切しておりません。「こころの疾患」の中には、薬物療法を第一選択とするものがあり、そのようなケースに対しては積極的に薬物療法を行なっています。またそれ以外の疾患においても、薬物療法を行なったほうが治療の進展が期待できる場合には、お薬をお勧めすることがよくあります。ただしいずれの場合も、処方薬剤数はできるだけ少なくし、依存性のあるベンゾジアゼピン系薬剤はなるだけ処方しないよう心がけております。